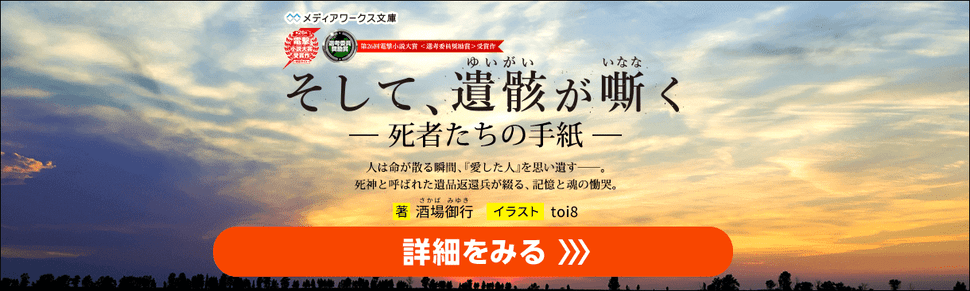一章 サリマン・キーガン――兵隊さんごっこ
ある日の朝目が覚めると、部屋のドアの前には長い丈のスカートとフリルのついたブラウスが置かれていた。
1
統合暦六四二年、クゼの丘。
一行は、屍(しかばね)となった戦友の上を歩いていた。
寒さと疲れで動きの鈍い足でぎゅむぎゅむと踏む度に、彼らの軍服の袖や裾に入り込んでいた薬莢が高い音を立てながら落ちていって、骸(むくろ)が嘶(いなな)いているようだった。
「くっそさみィ……なんで俺らがタグの回収をやらなきゃならん」
一行の内一人が心底疲れたようにぼやく。続いてああ、と真っ白な吐息交じりに出た声は、まだ丸い形を残していた腕を踏んで足を滑らせたことに対する苛立ちだ。その感情が伝播する前に、彼らの中で最も階級が高い上等兵が「まあ、そう言うな」とこちらも疲労の滲んだ掠れ声で言った。
「他に相応しい奴がいなかったんだろう」
「相応しい? 狙撃兵がです?」
「そうだ、比較的軽傷だろ。歩兵は皆手酷くやられてるし、将校殿らは作戦会議中だ」
「いやいや、俺らだって後半ずーっと駆け回ってたぜ。それにキャスケットさん、あんた大腿に二発食らったんじゃないのか」
「まあな……。正直かなり痛いし、この後ベーゼ軍曹も探しにいかなければならん。さっさと終わらせたいのはオレも同じだ。お前もぶちぶち言ってないで早く仕事を終わらせろ」
上等兵――キャスケットに半ば強引に諭され、不満を口にしていた兵士は黙って転がる死体の首元に視線を落とし始めた。深緑色の軍服は自国の兵士、黒色の軍服は敵国の兵士だ。前者は手で転がして検分し、後者は乱暴に蹴り飛ばして退かす。
十数人の兵士はしばらくそうしていたが、中々終わりは見えてこない。「埒があかないな」三十分ほどして、キャスケットが頭に被った軍帽とは違う帽子ごと顔を上げた。
「手分けしよう。サリマン、そこの五人を連れてあっちのタコツボの方を頼む」
キャスケットが先程から黙々と作業をしている一等兵にそう声をかけたが、彼は地面から顔を上げない。
「……サリマン?」
「……」
「……サリマン・キーガン一等兵!」
「んっ!? っはい!」
び、と猫が飛び上がるように、サリマンと呼ばれた一等兵が顔を上げる。煤だらけの顔に意図して無視したような色は見られず、キャスケットは溜め息を吐いた。
「まだ耳の調子は戻らんか」機関銃の銃声を聞きすぎて耳が馬鹿になってしまったと知っている上等兵は、少し気配りするようにそう訊いた。
「ああ、いや。それもあるんですが、終わった実感が湧かないと言いますか……申し訳ありません、少し呆けていたようです」
「張り手は兵舎に戻ってからにしてやる。そっちのタコツボ辺りのを頼む」
「は、了解です」
一等兵は、頭を下げ、数人の兵士と作業を開始した。
階級は違えど、この二人は同期だった。キャスケットはその顔がどこか緊張感を欠いていたのに気付いていたが、気付かないふりをして、また足元の兵士の首に下げられた認識票(タグ)を一枚千切り取った。
「平気ですかね、キーガンさん」
「なにがだ?」
「耳も悪くなってますし、ほら、あの人ちょっと抜けてるとこあるから……」
「あいつは……故郷に母親と兄弟を残してきているから、これで帰れると思って脳が緩んできてるんだろう」
戦いが終わった兵士が自分の帰る場所に思いを馳せることはなにもおかしいことではない。まだ戦場なのだから気を抜くなと怒鳴りたいところだが、キャスケットももう怒鳴れるほどの体力と気力は残っていなかったし、なにより、そのささやかな夢想を邪魔したくはなかった。
――その配慮が、過ちだったのかもしれない。
ぱん、と。
女の柔らかい手の平が誰かの頬を打つような、軽い銃声が空に響いた。
「――!!」
キャスケット含め、兵士たちは反射的に肩にかけていた小銃を素早く構えた。音のした方に体を捩ってから、それが先程キーガン一等兵たちが向かっていった方向だと気付く。
灰色の雲を伸ばした空の下、よく見知った緑の軍服を着用した兵士の後ろ姿が、ぐらりと傾くのが見えた。背中に赤い色が見える。その傍には半身を起き上がらせた黒い軍服の男がいて、間もなく体が地面に叩き付けられるであろう彼に拳銃の口を向けていた。
最初に撃ったのはキャスケットだった。中距離に対応する歩兵銃の撃針が雷管を叩く。放たれた銃弾は寸分の狂いなく敵兵の頭蓋を貫き、脳の神経伝達がめちゃめちゃになった敵兵の肉体は一瞬痙攣した。それに追い討ちをかけるように仲間の弾が同じように敵兵の頭部へ吸い込まれていく。
「くそ!!」
キャスケットが、喉を裂くようにそう吠えた。
敵兵の体が地面に伏したのは、撃たれた仲間が膝を折るのと同時だった。キャスケットが銃口を下ろし駆け寄る。――嫌な予感がした。予感というよりも、これまでの経験から来るもう少し具体的なものに近い。こういうとき、大抵、ロクな展開にはならなかった。
案の定と言うべきか、両膝を突いて左胸部を押さえていたのはサリマンだった。兄弟と母親を残してきていると話した傍からこれだ。彼と一緒にいた五人に「なに見てたんだよ!!」と怒鳴り付けている文句の多い一等兵を止め、衛生兵を呼ぶよう指示する。
「サリマン、おい」
は、は、とまるで嗤っているような呼吸を吐き出す戦友に視線を合わせるためしゃがみ込み、顔色を窺い、努めて穏やかに声をかけながら震える背中を擦る。
「意識ははっきりしてるな? 大丈夫だ、見せてみろ」
「……しんぞう……心臓近くを撃たれてる……」キーガン一等兵が、自己分析をするように言う。戦慄(わなな)くその唇は青く、唾液に赤い色が混ざっていた。
「大丈夫だ。肋骨と筋肉が守ってくれてる。――おい、鎮痛剤をよこせ。お前はガーゼ探してこい、布製のもんなら多少不潔でもかまわん。急げ!」
キャスケットはキーガン一等兵の大腿部に鎮痛剤を射ってから、左胸の両手をそっと退かした。途端、コップをひっくり返したように血液が溢れ、その背後で自分用の応急処置用品を取り出していた兵士が息を呑んだ。
駄目なやつだ、と。
その場にいた全員が思った。それは、キャスケットも、そしてキーガン一等兵も例外ではなかった。
「……キャスケット」
キーガン一等兵が、上官であるキャスケット(上等兵)を、かつて同期の同室だったときのように気さくに呼んだ。「なんだ」、声が上擦りそうになるのを耐え、答える。
「からだが動かない」
「……ああ」
「き、きずから、目が離せ……ない、んだ。自分が段々死んでいくのなんか見たくない……私は、家族のことを思い出しながら死にたい…………」
俯いたその口から、粘っこい喀血が、蜘蛛の糸が垂らされるように地面に落ちていく。
キャスケットはその願いにただ一言、「わかった」と応えた。
そうしてキーガン一等兵の体を横たえさせると、その両目の上に自分の手を重ねた。兵士の皮膚が厚くぼろぼろの手では、母や幼い兄弟を思い出すことは難しかっただろう。それでもキーガン一等兵は、視界が暗闇に覆われると安堵したように息を吐いた。
「あぁ……帰っ、た……あの、……、れもん……スを、……また……ォませ……ぁる…………」
ちいさな石が転がるように、ぽろぽろと。遠い故郷の何かを夢に見て、キーガン一等兵は呟いていた。それを、見込みのない励ましの言葉で邪魔する友人は、誰もいなかった。
統合暦六四二年冬、後に森鉄(しんてつ)戦争最大で最悪の戦線だったと呼ばれるクゼの丘。
自国の死傷者一万五千を超えたとされるその場所で、その内最後の一人が、出血多量によるショックで死んだ。