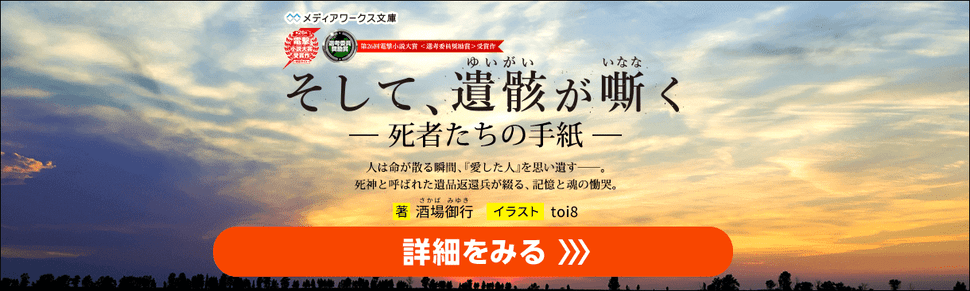3
夜を迎え、硬いベッドに入る。目を閉じれば疲れ切った体は直ぐに弛緩し休息を受け入れた。
二年前に終戦してからだろうか。この頃、アルマは毎晩悪夢を見る。
夢の中で、兄が帰ってくるのだ。扉を開けた先に血と泥を被った兄が立っていて、アルマを見下す。体中の肉が裂け、抉れ、あるいは砕け、傷口に蠅の卵を産み付けられたその姿。漂う死臭に夢だとわかっているはずなのに、心が現実だと認識してしまう。
「なんだ、そのみっともない恰好は」
兄の口から落とされた言葉に、まるで氷柱で喉を裂かれたような恐怖がアルマを襲った。兄はアルマの肩を掴むと、指を食い込ませて、真っ赤になった目を破けそうなほどに見開いた。
「俺が――俺が戦争に行っている間!!! お前は何をしていた!?」
見ろ、この指を!と兄がアルマの眼前に欠損した手を突き付けた。その拍子に卵が撒き散らされて、二人の足元に乳白色の粒がぼとぼとと落ちていく。
「こんな、こんな指じゃあ、もう医者にはなれない……! わかっていた。でもお国のためにと耐えて耐えて耐えて、俺は立派に成し遂げた、名誉の死を! だのにお前は――お前は!」
兄は泣いていた。夢だからだろう、アルマには、それが絶望の涙だとわかった。やがて兄の顔は蛆に埋め尽くされ、その姿は砂の城が崩れるように消えていった。
残ったのは、耳障りな羽音を立てる蠅と乳白色の卵が散乱した玄関。
いつもなら、そこで夢が終わった。目覚めてまた一日が始まる。だが――今回は、目が覚めなかった。不思議に思っていると、足元の卵が一斉に孵化し、蛆が蠅に育ち飛び立った。家の外ではない、中へ――
「……!!」
家。父が残した、かび臭い小さな家。きしきしと鳴る床、洗い物の溜まったシンク、枯れそうな観葉植物。それらが飾られた室内へ蠅たちを追って視線を転じさせると、ベランダから入った日の光を背に一緒に洗濯物を取り込んでいる母と妹の姿が見えた。
――だめ。
――二人だけは!
「止めて!!」
叫んで駆け出した。振り乱した髪の先で笑う二人がこちらに視線を向けたと思った瞬間、夢は終わりを迎えた。
目覚めた場所は、ベッドではなく、テーブルの上だった。顔を上げると手には糸の繋がった針と丸い刺繍枠が取り付けられた布。どうやら、内職中にうたた寝していたようだった。
は、と息を吐いて、椅子の背凭れに寄りかかる。悪夢の内容は毎度変わらなかったが、今日のは特に酷かった。母と妹が出てきたことなんて、初めてのことだったのだ。二人だけは。二人だけは、自分と兄とは違うはずなのに。
「……」
母の言う通り――父の遺産を考えれば、仕事なんてこの内職だけでいい。当分はこれで食いつなげる。けれど、町の住民から時折与えられる暴力に対する嘘の理由がほしかった。山向こうの町で行う決して安全ではないプレス工場での仕事は、そういった点で実に役立った。たとえ体力のほとんどを費やされ、ときに頭が痛み足元が覚束なくなっても。
刺繍はツイタチソウの半分を描いてテーブルに放置されたままだったようだ。続きをしようとしたところで、妹が遊びにやってきた。手に毛布を持っている。
「なにしに来たのかな、可愛いお嬢さん」アルマがからかうように言うと、妹は「おねえちゃん寝てたでしょ」と言ってアルマの膝に毛布を置いた。
「……毛布持ってきてくれたの?」
「だって寝るときは毛布がいるでしょ?」
「ありがとう。でも、大丈夫だよ。もうたくさん寝たから」
「ふうん」妹は納得しているようなしていないような態度で鼻を鳴らした。それからアルマの膝の上によじ登り、よいしょと腰を下ろし、手元をじっと見詰めた。妹ももう八歳近くなるから中々重い上視界がかなり妨げられるが、アルマはそれを許し、刺繍を再開した。
「おねえちゃん」
妹が顔を前に向けたままアルマに呼びかける。
「ん?」
「おにいちゃん死んじゃったの?」
針の動きが止まった。アルマは注意深く呼吸を重ね、「どうして?」と訊いた。
「おかあさんが泣くときって、誰か死んじゃうときでしょ。おにいちゃん死んじゃったの? だからまた兵隊さんが来たの?」
「……うん。父さんのときと、同じ。死んじゃったときに持ってた持ち物を、届けに来たの」
乾いた舌でなんとか音を出した。「ふーん」と、また不明瞭な返事。
妹は兄に会ったことがない。彼女が生まれる前に、兄が徴兵されたためだ。
油が撒かれた床に火の付いたマッチ棒を落とせば瞬く間に炎が広がるだろうが、そうでなければ小さな焦げ跡がつくだけで火種は消える。同じように、悲しみ苦しむほどの思い出がないのなら、手の平で覆うほどの涙は出ない。妹の感情は筋が通っている。
では、自分は。確かに遊んでもらった記憶は少ない。兄に対して抱いている感情は良いものばかりではないけれど、それでもなにかしらの情はあったはずだ。それなのに――。
――あの手紙を読めば、なにか変わることはあるのだろうか。
妹を膝に乗せたままで椅子に座りそうやって窓の外を眺めて悩んでいると、妹が「おねえちゃん続きチクチクしないの?」と布と針を危なっかしく持って問いかけた。それをするりと取り上げ、「やるよ」と上から顔を覗き込む。妹は、アルマが刺繍をする姿を見るのが好きだった。
「おねえちゃん、綺麗だけど、縫うのは遅いのね」最近ますます達者な口を利くようになった彼女はアルマと母とを比べてそんなことを言った。
「私、指が長いんだもん」
「貸して!」
「だめ、危ないから。刺繍は八つになってから。もうちょっと待ちな」
むくれた妹は膝から下りて台所の方へ行ってしまった。その内戻ってくるだろう。アルマは視線を下に落とし、どうすれば兄の遺品を受け取れるか――『弟』の代役を立てるか、あるいは真実を話そうか――考えながら、ツイタチソウを黄色の糸で縫っていった。
刺繍が終わったのは昼手前頃だった。その頃になると大分頭の中が整理出来て、やはり正直に話そう、とアルマは椅子から立ち上がった。
母の寝室を覗くと、呆れたことに妹は母と一緒に布団にくるまって眠り込んでいた。夜になって寝れない寝れないと愚図っても知らないぞ――小さく溜め息を吐いて、アルマはそっと扉を閉めた。
一応リビングのテーブルに『外に出てます』と置き手紙をして、アルマは昨日の大衆食堂に急いだ。弟を連れてまたここへ、と言われていたのだ。
酷く静かなアルマの家に反し、市場はやはり多くの人で賑わっていた。例の大衆食堂に行くと、昨日のことを覚えていたらしい女将が「昨日と同じ席にいるよ」そう教えてくれた。
「兵隊さん」
声をかければ、甘ったるそうな蜂蜜色の目が振り返る。
「来たか」
「はい。すみません、何日も」
向かい合った椅子に座り、頭を下げる。
「いや。オレ……私たちは、望めば数日間軍の資金で一ヶ所に留まることが出来る。なにも迷惑していない」
ぶっきら棒に言う兵士は、やはり昨日と同じように柑橘系の飲み物を、と注文した。それも経費なのかと問えば、本当はダメだけど内緒だ、と返ってきた。変化に乏しい表情に反し思ったよりも人間らしい回答に、アルマはくすりと笑みを溢した。
少し、沈黙が流れた。しかしそれは昨日のように言葉に詰まったそれではなく、アルマが次の言葉を口に出すまでの準備時間で、彼女が想像していたよりも短く済んだ。
「……兵隊さん」
「ああ」
「……弟は、」
「お前なんだろう?」
――私なんです、と。
そう続ける前に、兵士が同じ内容を口にした。
彼女――否、彼――サリマンの弟は、
「……どうして………」
長い丈のスカートを握り締め、ブラウスに汗を滲ませて問う。
「……サリマンは、オレの同期だった。毎日うるさく、オレと同じくらいの歳の弟がいると話していた。焦げ茶の髪に眉の上のホクロが自分とお揃いなのだと。失礼だが戸籍を調べさせてもらった。キーガン家でサリマン以外に二十歳以上の子供は一人だけだ。アルマン・キーガン、お前がそうだな」
琥珀色の目が、じっとアルマンを見詰めた。途端顔に血が一気に集まり、羞恥に俯く。――だって、目の前のこの人は、町の住民と同じように自分のことを知っているのだ。二十を超える男が女物の服を着て、髪を長く伸ばし、そして性別を偽って徴兵から逃れた卑怯者だということを!
話さなければ、そう思った。このままでは責められてしまう。軽蔑の眼差しで責め立て、非国民と罵り、あの兵隊さんごっこをしていた少年たちのように銃剣を突き立てるかもしれない。煮えて馬鹿になりそうな脳になんとか命令し、アルマンはふうふうと余分に息を吐き出す唇を開けた。
「……は、母が……、男子では、兵に取られるから、と」
そうだ。
父と兄が軍に取られて数日後――ある日の朝に――部屋のドアの前に、長い丈のスカートとフリルのついたブラウスが置かれるようになった。
「十三のときから、ずっと……」
アルマンは、それを拒否出来た。母は非力で弱々しいから。でもしなかった。それは――
「父も兄も取られて、身重の母一人置いて家を出るなんて出来ません。私は……」
きっと、こんな建前の理由ではない。
あの頃『兵隊さんごっこ』をした男友達は皆兵士になった。隣の家のシルヴィ。向かいのレノン。工場で一緒に働いている男性も、それにこの食堂の隻腕の息子も、帰還兵だ。アルマンだけだ。アルマンだけが、家に残った。何故。理由は沢山あった。心の弱い母を支えるため、小さな妹の面倒を見るため、父が残した家を守るため、兄の代わりになるため――それらに嘘はきっとなかったはずだけれど。今となっては、本当の理由はわからない。
あるとすれば、きっとそれは一番卑しくみっともないものじゃないだろうか。そうだ、母の馬鹿げた要求を拒否しなかったのは、スカートを穿いたのは、口調も全て直したのは――去勢までしたのは。
ただ単に――戦争に往くのが恐ろしかったからだ。
兄の訃報を知ったとき、悲しみよりも先に「ああ、戦争に行かなくてよかった」「私は家に残ってよかった」、心の底からそんな声が聞こえた。これが本音だ、この声こそがきっと本物だ。兄が帰ってきて女の恰好をした弟を見たら、彼は間違いなくあの悪夢そのままにアルマンの肩を揺さぶったはずだ。その恐怖を回避出来たことに、アルマンは安堵した。
「……私は、……」
続けられぬ言葉の代わりに昨日のように唇を噛み締めた。今日は檸檬の味はせず、少し苦い感じがした。これは、皮膚の味だ。
徴兵を逃れるための身分詐称は重罪に当たる。そして目の前にいるのはこの国を統べる父の子たる兵士だ。叱責とともに鉄拳が飛んでくるだろうと俯き身構えていると、
「そうか」
兵士はただ、それだけ言った。
「え……?」
「オレは……お前が身分詐称をしていてもどうでもいい。オレの仕事は遺品を届けることだ。お前が『サリマンの弟』なら、それでオレは仕事を完遂出来る」
彼は鞄から、あの封筒を取り出した。
乾いた血液と泥にまみれたそれをアルマンがそっと受け取ると、パリパリと音がして、テーブルの上に土塊が薄く積もった。
「……」
封筒の表には、弟へ、と書かれている。
指先で探った中身を取り出すと、中の便箋には、『拝啓、弟へ』から始まる内容が書かれていた。
そのとき脳裏に、しばし女性的だと表されたあの太くもすらりと長い兄の指で髪を梳かれたような感触が過ぎった。むず痒さに似ているそれを紛らわすために後頭部を自分で撫でる。
兄はきっと、汚い手段を使って徴兵を逃れた自分を恨んでいるだろう。憎んでいるだろう。あの夢のように、自分を責め立てる内容がそこにあるかもしれない――。一つ大きく息を吸って覚悟を決めると、アルマンは少し乱雑な字体に視線をなぞらせた。
『拝啓、弟へ。
元気ですか。兄さんはそこそこ元気です。
兄さんはこれから、クゼの丘という場所に戦いにいきます。とても厳しい場所だと聞いていますが、それに勝てればこの戦争がどうにかなりそうというので、どうにかなったらいいなぁと思っています。
さて、今回手紙を書いたのは、兄さんの上官(兄さんの兄さんみたいな人です)に遺言を残せと言われたためです。とはいえ、兄さんが死んだらお前たちの食いぶちが父に頼りきりになってしまうので死ぬ気は更々ないのですが、そうも言ってられんのが今の戦況です。というわけで、今、家を任せているアルマンに、もし兄さんが死んでしまったらやっておいてほしいなってことを書き出しておきます。
いち。引き続き家を護ること。
に。泣き虫な母さんを見放さないこと。
さん。末の子にせがまれたら、俺が死んだことを含めて存分に話すこと。
これくらいかな。
家で唯一残った男子のお前に、色々なことを任せてしまって、兄は申し訳なく思ってます。でも兄さんも父さんも直ぐに帰るので、それまで頑張って!
あと十五分で召集がかかり、列車と徒歩と船で丘へ向かいます。それではまた。
六四二年秋の終わり サリマン・キーガン』
一連を読み終わり、
アルマンは、なにも感じなかった。
「……、」
ぎゅう、と胸元を握る。
――自分にはこころというものがないのだろうか。
兄の、ことを。
ああ、死ぬ気はなかったのだなぁとか、遺書なのにもうすぐ帰りますとか書いていて馬鹿のようだなぁとか、そういう、少し心が擽られるような感想は、確かにアルマンの中に浮かんだ。自分が戦争に行かなかったことを知っているはずなのに、その理由についてたったの一つも触れていないところにも、喉の奥から込み上げる何かはあった。
それでも――それでも。
「……案外、悲しくないものなのですね」
アルマンは冷静だった。自嘲のような言葉に、兵士が相槌を打つことはなかった。
アルマンは静かに手紙を元の通りに折り畳むと、封筒に仕舞おうとして――
「……?」
中に、もう一枚。今しがた読んだ用紙よりももっと汚れた、何かの書類らしきものが入っていることに気付いた。
取り出し、半分に折られていたそれを広げる。そこにサリマンの字で「追伸」から始まる文が綴られていた。
『追伸。アルマン、お前は昔、よく兵隊さんごっこをしてほしいと強請ったけど、
兄は、それが大嫌いでした』
「……、」
え、と。小さく声が漏れた。
――嫌い?
――そんなこと、一言も。
兄が遊びを断る理由は、いつだって『勉強で忙しいから』だった。勉強、そう、勉強――。
『兵隊なんて嫌いです。誰かを守るための手段に殺人が含まれるからです。
アルマン、お前は優しいから、本当はやりたくなくても家族が仲間外れにされないように、遊びに加わっていたね。
同じように、お前は今、苦しい道の中にいるのでしょう。兄は、お前がたくさんある苦しみの中で一番苦しい道を進み、その先で優しさを見付ける人間だということを知っています。自分がどれだけ傷付いても誰かにとって最良の選択をする。兄はそれを、羨むくらいに尊く思っています。
寂しい思いをさせてごめん。苦しい道を歩ませてごめん』
字は所々風に吹かれる灯(ともしび)のように揺れて、読むことが難しかった。けれどアルマンは、親指で文字をなぞりながら、ときおり視線を躓かせながら、読み進める。
『それでも兄は、お前が生きていると知って、この丘には来ていないと知って、心の底から安堵しました。お前が生きていることが活力になりました。どうかこれからも生きてください。寂しくて苦しくても生きてください。それだけが、兄の願いです』
最後の一文字に視線を伸ばし、それから最初に戻ってもう一度じっくりと読んでから、アルマンは、顔を上げた。
「同期と……そう言われましたか」
「ああ」
「兄の……兄の死に際がどういったものだったか、ご存じないでしょうか」
望みの薄い質問だ。クゼの丘戦線は三万人以上の人間が入り乱れた攻防だったと聞く。その中でたかが一等兵が死んだ瞬間など、誰の記憶にも留まらない。
そのはずだった。
「知っている」
「え、」
「聞いて後悔しないか。あまりいいものではないが」
蜂蜜色の瞳に問われ、アルマンは唾を飲むと、静かに頷いた。
「サリマン・キーガンは優しさと頭の良さしか取り柄のない男だった。剣術も銃術も体術も成績はあまり良くなく、しかし『家族のもとに帰りたいから』と毎回しぶとく生き残った。そういう男は、案外最後まで生き延びる。最後というのは、戦争が終わるまでだ。けど死んだ。戦場で殺られたんじゃない。わかるか」
「いいえ――」
「あいつ――死体のタグを回収しているときに、死にかけた敵兵にでくわしたそうだ。そいつが『水、水、……』って、そう言っているのを、なまじ頭が良かったから、それがわかってしまったんだ。それで自分の水筒の蓋を開けようとしてる最中、その敵兵に鉄砲で撃たれて死んだ」
また、沈黙が二人の間を満たした。隣の席の夫婦が立ち上がり会計を終えてから、乾燥した唇は震えながら動いた。
「兄には、友人がいたんですか?」
「両手では数えきれないほどに」
「兄は、医者になりたがっていましたか?」
「衛生兵の手伝いをしているところを見かけたことは何度もある」
兵士は淡々と答える。
馬鹿な兵士(兄)だと思う。敵に情けをかけて殺されてしまったなど、間抜けもいいところだ。
けれど――ああ、その行いは。
濃緑色の軍服を纏い、蛆に塗れ怒りのまま言葉を吐く兵士ではなく。
机に向かっている背中に声をかけたときに振り返った、困った顔の青年。
アルマンが知っている兄の姿だった。
「なんだ……生きてたんだ」
そう、アルマンは溢した。
兵士が、首を傾げる。言外に否定している。「お前の兄は殺された」と。
「……違うんです。体の話じゃなくて、ただ……兄は、私の知っている兄のままだった……。……うん。そうだった。兄さん、私が生き延びたことを恨んだり、軽蔑して責め立てるような人じゃ、なかったよね」
肉体は死んだ。でも、戦争に行っても兄は自分の知っている兄だった。医者になりたがっていた、ただの若者――それが兄の核、兄の魂。腰に抱き付くと大きく手を広げて抱き締め返してくれた、優しい兄さん――。
だからアルマンは、静かに頷いた。兵士は目を伏せ、「そうか」と端的に返す。
そしてアルマンは、背筋を伸ばした。
「サリマン・キーガン一等兵の遺品、その弟、アルマン・キーガンが確かに受け取りました」
「……サリマン・キーガン一等兵の遺品、確かに引き渡した」
間もなく、昨日と同じ檸檬のジュースが届いた。爽やかな甘味のあるそれを、アルマンはゆっくり味わって飲み干した。やはりなんとなく懐かしい味がしたけれど、いつどこでどんな理由で飲んだことがあるのか思い出すことは、終ぞなかった。
兵士の去り際に、アルマンは彼に名前を聞いた。
「オレか?」
「はい」
「……『キャスケット』だ。兵士になってからはそう名乗っている。もしお前が兄の後をなぞりたいと考えたなら、東北部方面軍第一師団でオレの名前を出せ。いくらか助けになるはずだ」
兵士――キャスケットは、自らと同じ名の帽子の鍔を緩く押し上げ、それからどうしてか「ありがとう」と言って別れを告げた。
アルマンが家に帰ると、母は台所に立ってシチューを作っていた。
安価だけれど美味い牛乳と、煮込まれた野菜と肉が混ざったやわらかい香りが満ちた空間。アルマンが自分よりも幾分か細い背中に「ただいま」と声をかけると、尖り気味の顎が少しだけ振り返って「おかえり」と動いた。妹の所在を尋ねると、外に遊びに行ったと返ってくる。
「母さん、あのね」
「ん?」
「兄さん、死んだって」
くつくつと、シチューの表面に泡が浮かんで弾ける音が耳に届く。しばらくすると、母の背中が震え出して、小さく嗚咽が漏れるようになった。アルマンはその背に近寄り、火を消すと、母の背を擦った。
「ごめんね、母さん。ごめんね。大丈夫、大丈夫……」
いつも通りの慰めだった。でも伝えなければいけない。兄のことを、彼女に。
兄が兵士を嫌いなら、アルマンは――兄が好きではなかった。
医者になるための勉強ばかりで、かまってもらった記憶は薄い。
たまに都会の土産と手紙を送るばかりの遠い遠い存在のくせに、誰もが尊いように扱う。
顔も朧気で母の心労の原因にばかりなる彼のことを正直疎ましくも思っていたし、帰ってきて自分をあの悪夢のように責めるだろうと恐ろしく感じていた。
母の背中に手を当てていると、母がゆっくりと首を横に振った。
「ちがう、ちがうの……アルマン、私は、お前のことが悲しいの」
「……私?」アルマンは、首を傾げる。
「お前が、優しい良い子だから、それに甘えてしまった。行かないでって言えば頷いてくれるとわかってて、でも言葉にするのは怖いから服を着せたの。私がそんな苦労ばかりかけたから、泣けなくなってしまったんでしょう? ねえアルマン、ごめんなさい。私、お前にたくさん酷いことをしたわ……」
ぶどうのように大粒の涙が床に落ちていく。母が自身を責めているのだと気付いて、アルマンは静かに首を振った。
「違うよ、母さん。私は……私は多分、泣く必要がないから泣かないのよ」
シワの刻まれた目元がアルマンの方を向く。
思い出が少ないから。煩わしかったから。自分の心が反応する場所を見失っている。だから涙が出ない。
あの兵士が来るまではきっとそうだった。けれど今は、おそらく、そうではないのだ。
「母さん、あのね。兄さんは、人を助けようとして、それで死んだのだって。呆れるくらい、優しいでしょ」
女物のブラウスの袖で涙を拭ってやりながら話す。
「私も……きっとそうよ。兄さんが言ってくれた。一番苦しい道を選ぶ優しい人間だって」
一番苦しい道。戦争に行った方が楽だったとは言わない。けれど、戦争に行っていれば、非国民呼ばわりされ町の人間から酷い扱いを受けることはなかっただろう。
――あの日置かれていた服を着ることを選択したとき、そうすることで周囲からどんな扱いを受けるか、わかっていた。
「兄さん、私に言葉を残したわ。これからも引き続き、家を護り、母さんを慰めて、妹を愛せって――これなら別に、スカートを穿きながらでも出来るから、母さんが安心するなら、私はそれでもいいよ。それがいいの」
母はある日の朝、部屋のドアの前に服を置いた。
兄は戦争から逃げられなかった。十四歳を超えた男だったから。医者を目指したのに、正反対のことをすることになった。母は、これ以上子供を連れていかれる苦痛から逃れるために、衣装棚を開いた。
それを受け入れた自分は脱走兵よりも恥ずべき弱虫だ――ずっとそう思って生きてきた。親しかった近所の人から侮蔑の視線を寄越されても仕方がない、そう俯いて、ひっそりと呼吸をする。そんな毎日。
だが、違った。母の涙も、妹の笑顔も、間違いなく大切なものだった。一番大切で、一番苦痛に満ちた我が家。――もっと単純なことだったのだ。戦地ではなく、直ぐ近くで守ろうと、そう決めただけ。方法が異なるだけだった。兄は戦争に行くことで家族を守った。アルマンは家に残って母と妹を支えた。兄がそう言ってくれた。認めてくれた。許してくれた。
そのとき妹が泥だらけで外から帰ってきて、台所で号泣する母と慰める姉を見て「喧嘩ー!?」と大声で言いながら困惑した。
アルマンはそんな愛しい存在を抱き寄せ、おかえり、と告げた。
後日、アルマンは山向こうの工場で夜勤に出た。
工場の人間はアルマンの事情を知らない。それをずっと心地よく感じていたけれど、今は少しだけ、ここを辞めようかと考えている。心配性な母のことを考えると長い時間離れていることは心苦しかった。家で家族と過ごすか、町で働かせてもらえる場所を探してみようか――そこまで考えて、アルマンは苦笑した。なるほど確かに、自分は結局のところ苦しい道を選んでしまう傾向があるらしい。
夜が明け、アルマンは工場の外に出た。夏の太陽はまだ寝惚け頭らしく、陽射しは彼女の頬に優しく口付けを落とした。
そこに、
「アルマちゃん」
一人の男性が、歩くアルマンの隣に駆け足で並びながら声をかけた。欠けた片耳。西部で徴兵され兵士として勤めていた男性で、工場でいつも昼の時間帯に一緒に働いていた。確か名前は――
「……ええと」
「ウィル! ウィル・レヴァノ。なあ、山向こうから来てるんだろ? 俺もそっちなんだ。一緒してもいいか? 作業のことでさあ、ちょいと訊きたいことあんのよ」
そんなの仕事中にすればいいのにと思いながらも、アルマンは頷いて返した。ウィルは喋り好きな性格なのか、最初は金属板を設置するときのことだとかこっちの手が詰まったら少し待ってほしいだとか仕事の話をしていたが、段々と自分の家族のことや帰り道で見付けた変な形の石の話をし出した。不思議と煩わしさは感じず、アルマンは時折微笑みながら相槌を返した。
「なあ、ところでさ」
二人が別方向に向かう分かれ道の数十メートル手前で、ウィルは軽い調子で切り出した。
「いつも昼とか午後の早くとか変な時間で帰っちまうけどさ、なんかあるのか?」
あまり重要な風ではなかった。本当に、なんとなく訊いたのだろう。
ただアルマンにとってその理由を嘘偽りなく答えることは、非常に言葉に詰まるものだった。故に足を止め、彼がこちらに注意を向けるのを待った。ウィルは急に立ち止まったアルマンを見て、不思議そうに片眉を上げた。
「……どうした?」
「……誰もいない時間帯に、更衣室を使いたかったの」
ウィルは目を泳がせ、それから気まずそうに後頭部を掻いた。おそらく、体になにか傷跡があるとか、そんな風に受け取ったのだろう。以前ならばそう思われることは好都合だと感じた。けれど今は、胸に枯葉を詰められたような罪悪感が募るだけ。
「それは……」
「男なんだ。女の恰好をしてる。十三のとき、徴兵を逃れたくて。それからずっと女のフリをしている」
これ以上にないほどに簡潔な回答を述べた。言い切ってから、アルマンは自分の声が震えていたことに気付いた。掠れた言葉尻を舌で転がして、相手の反応を待つ。
ウィル――戦争で耳を削られた彼は、脳内でアルマンの言葉を咀嚼して、ようやくそのままの意味だと理解すると、目を細めた。
「……どうして、そんなことを?」
「……母親と妹を、戦争に行ってではなく……家の中で、直ぐ傍で、守りたかった」
緑葉が濃い臭いと木漏れ日を撒き散らしながらざわざわと揺れた。嘲笑っているようでもあった。アルマンは爪先からゆっくり這い上がる恐怖に負けるものかと、しっかりと足を踏ん張った。
どれだけ非難されてもいい。明日にはこの話が工場の人間全員に知れ渡り、また一つ居場所を失うかもしれない。けれどこれが自分の本当だ。見失ってしまっていた、選んだ道。
ウィルは目を見開き、歯を噛み締めるとアルマンに向かって一歩大きく踏み出した。そして、細い肩に掴みかかる。殴られる、そう思い反射的に顔を背けたとき、
「――その手があったか!!」
まるで研究者が生涯に一度の閃きを得た瞬間のように無邪気な声色。アルマンが顔を上げると、そこに興奮に頬を染めたウィルがいた。
「ははあ~~なるほどねぇ! いやよく思いついたな、凄いぞ! 俺はさあ、神学校の生徒でもないし都合よく負傷して帰れたわけでもなかったからさァ、ずるずる前線まで行っちまって、でも戦争終わらんで帰ったらなんか言われるだろどうせ? 地元のやつにバレねーもん? あ、それでこんなとこまで働きに来てんのか!」
パチーンと指を鳴らし合点したと言いた気に深く頷くウィル。アルマンは面食らってしまって、肩を揺らされながら目を丸くした。
「あ? どうした?」
「……いや……普通、怒るものでしょう」
「なんで? 俺と君の人生、関係ねえし。家族を守りたかったってのもわかる。戦争に行こうが、家にいようが、どっちも苦しくて辛いなら自分が行きたい方に行ったってだけだろ。それは誇れることだ」
なんともないように言ってからしきりに感心したように「盲点だった」「いや、でも俺が同じことしたらすぐバレるな」と頷き続けるウィル。アルマンは、ぎゅうと唇を噛み締めた。与えられた肯定に、兄が生きて帰ってきたら、きっとこんな風に「なるほど、その手があったな」と笑ってくれただろうと思った。
――兄さん。
――母さんは体調を崩しがちだけど。妹はまだ小さいけれど。
――私もまだ、苦しいことは多いけど。
けれど――こうして気持ちをわかってくれる人を、一人見付けた。
それはなんてささやかで、しかし震えるような幸福だろう。
――生きていこう。生きなければ。
――寂しくても、辛くても。
――自分が選択したことを後悔しても、苦痛に思っても、誇りを持たなければ。
――そうすることだけが、歩んだ道に報いる方法なのだから。
これから先、苦痛と後悔に全ての時間を費やされようとも、与えられるぬくもりだけは手放さない。守り続けてみせる。この決意だけは真実だと、彼女は確信出来た。
けれど、思うのは。亡くなってしまった彼のこと。
妹や母――守るべき人たちの中に、兄もいてくれれば。
兄が、帰ってきてくれたら――アルマンは、木漏れ日が散る視界を閉じ、心の中でそう呟いた。