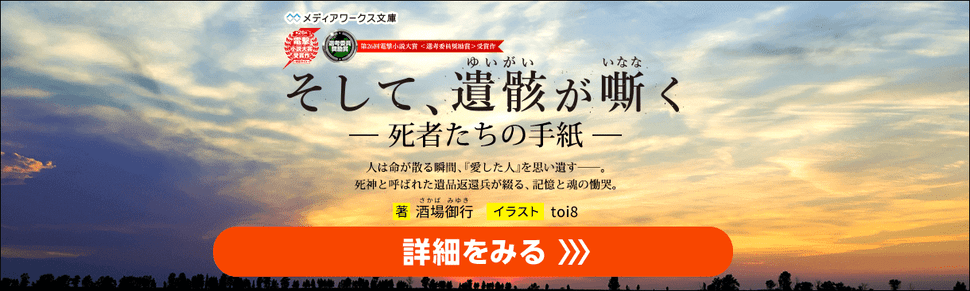4
サリマン・キーガンはアルマンの兄である。兄は弟よりも先に生まれてくるから、弟に優しくしたり、弟と一緒に遊んでやったり、弟を抱き締めてやったりしてやらなくてはならない。両親が弟のことばかり贔屓することもあったし「お兄ちゃんでしょ」と言われて我慢を強要されたりなんてこともときにはあったが、サリマンはそういったことを苦痛に思ったことはあまりなかった。なんと言っても小さな弟はふわふわしていて可愛らしかったし、医者を目指したきっかけというのも、弟がまだ母親に抱えられていた頃はたいそう体が弱くて、冬が来る度に熱を出す彼を治してやりたいと思ったからだった。
父のことも母のことも大事だ。けれど、兵士になってから思い出すのはいつだって弟のことばかりだった。家族という社会の中で初めて出来た自分よりもか弱い存在。優しくて小さな、私の弟――。
そんな弟が生まれてから、八年目の夏のことだった。
「兵隊さんごっこ』?」
幼い弟が誘った遊びの名前が、それだった。
サリマンはその名称から反射的に嫌悪を露わにした。昨日熱が下がってまた元気よく外に駆けていった弟は直ぐに飛んで帰ってきて、兄にその遊びに参加するようにお願いしたのだ。
――兵隊さんごっこって。
――あの棒切れを振り回して軍隊の真似をして遊ぶやつか?
「……、ごめんよ、アルマン。兄さん勉強で忙しいんだ。お前だけで遊んでおいで」
弟に背を向け、机に向かい直す。勉強というのは建前だった。そんな残酷な遊びに付き合いたくないというのが、サリマンの本音だった。
弟――アルマンは少し黙りこくって、俯くように神妙に頷くと再び外に出ていった。
弟は賢い子だった。自分や他人の気持ちを無意識下で読み取って行動するきらいがあり、サリマンが嫌がるようなことを一切やったことがなかった。そんな弟が、医者を目指している自分に『兵隊さんごっこ』だなんて。少し失望に似た気持ちが過ぎったが、けれど彼が一人の人間として自立し始めている傾向だろうと、そのときは受け取った。
サリマンが生まれ育ったペリドット国は、スモークォ国との戦争以前から森や土から生まれる豊富な資源を周辺諸国から狙われ国境付近でいざこざが絶えなかった。数年経ち彼が十六の頃は志願兵だけでは戦力が足りず、弟の十三の誕生日の翌月に第一期の徴募兵として軍都に来るよう彼に通達があった。
父は元から軍人でも、歩兵や狙撃兵ではなく軍医だったからまだよかった。長男である彼が戦争に行かねばならなくなって、体と心の脆い母は唸り声を上げながら泣いた。医者を目指し人の命を救うはずだった息子が反対に人殺しが主な仕事になる時代にその職業に就くことになってしまったのだ。泣くのも仕方がないだろう。
出立の日、彼は弟に大衆食堂の檸檬ジュースを奢ってやった。美味しそうににこにこと頬を緩める弟。なんとなく気になって、サリマンはこう訊いた。
「なあ、アルマン。お前まだあの遊びをしているのか?」
「花占いのこと?」
「いや……『兵隊さんごっこ』の方だ」
「うん」と弟は頷いた。サリマンは悲しくなった。戦争なんて、いいものではないのに。子供は、敵をやっつけることは正義であると学び、愛国心が強いほどに遊びを通して敵を倒すことへの達成感を育てる。大人はそれを止めずに、将来は立派な兵隊さんねなんて笑う。サリマンにはそれが酷く歪で恐ろしいものに見えた。彼らはわかっているのだろうか――自分の子供が、自ら死に近付く予行練習をしていることに。
サリマンは弟に死んでほしくなんかない。遊びだって止めてほしい。そう伝えようとしたとき、弟は思いもよらないことを口にした。
「別にやりたくないけど、やらないと『ヒコクミン』だから」
「……、非国民?」
「うん。ヒコクミンは家族も皆怒られるんだ。だから僕が皆を守らないと」
「――……」
サリマンは、弟と十三年過ごして、ようやく本当の意味で彼の賢さと優しさに気付いた。
――この子は、
――わかっているんだ。自分が起こす行動が与える家族への影響の全てを。
――その中で、一番苦しい道を選び取り、その先で優しさを見付けている。
――そんな風にしか生きられない星の下に生まれている。
聡い子供だとはわかっていた。理屈や理由を考える前に最良だと思う選択をする。どれだけ苦しい道が待ち受けていても、選んでしまう。
「……アルマン」弟に呼びかけると、丸い瞳がこちらを向いた。両手の中で握られた檸檬ジュースの中で、氷が音を立てる。
「……これから先、苦しくて辛いことばかりかもしれない。幸福に生きてくれなんて無責任なことは言えない。けれどどうか、……お前が、世界で一番優しい人間だということを、誇りに思ってほしい」
アルマンは難しそうに僅かに唇を突き出し、うん、と曖昧に返事をした。忘れてしまうだろうか。あまりかまってくれなかった兄の言葉なんて、些細な記憶として一晩夢を見れば消えてしまうかもしれない。それでも言葉にせずにいられなかったのは、彼が弟を愛している証だった。
寂しい気持ちのまま、かくしてサリマンは軍都に赴いた。彼は毎週手紙を書いた。家族との約束だったからだ。たまに、都会でしか売ってないような本や菓子を少ない給料を削って購入し一緒に送った。家族とのやりとりがあれば、態度と性格の悪い古年兵に理由もなくぶん殴られても、六年間、頑張ることが出来た。
六年後、統合暦六四二年。クゼの丘での戦いが始まると、まず隣の寝台で寝ていた古年兵が爆弾で四肢を破壊されて死んだ。分隊長も小隊長も次々と宙を飛来する弾丸に倒れ、その度に上官が入れ替わった。一段落着く頃には、見知った顔は同期の上等兵と他数名の兵士のみで、サリマンは十数年を費やした自分の医療の知識が戦場では赤ん坊が買い物を手伝うよりも役に立たないことを悟った。
死んでいった彼らの中で、印象的な死といえば、ある古年兵の最期だった。
その兵士は八年軍にいてもほとんど昇進せず、一年で上等兵まで上り詰めたサリマンと同室の戦友とは大違いだった。おまけに陰湿で嫌味な奴で、悪質な嫌がらせをよくしていた。しかし驚くべきことに、そんな彼が死んだ理由は、地雷に足を乗せてしまった仲間の身代わりになったからだった。
スモークォ製の地雷は踏んだ瞬間ではなく踏んで足が離れた瞬間に爆発する。だから理論的に言えば、乗った重さがたもたれれば爆発はしないのだ。それでその古年兵は、片足も地面から離せなくて泣いている仲間の代わりに自分の足を乗せ、仲間を遠くに逃がした。そして出来る限りのスモークォ兵を自分の周囲に誘(おび)き出し、足を離した。「森緋(しんぴ)の国ペリドットと我らが三人の父に万歳」と叫んで。
初めてその話を聞いたとき、彼は――サリマンは、それが自分の知っている古年兵とはにわかに信じられなかった。
そんな高潔な去り方をした人間が、サリマンを突然殴って「なんで殴られたか言ってみろ」「そうかそう思うのか、ならそうだ」と笑った男と同一人物だなんて、考える前に脳が拒否する。でも事実なのだ。悪い意味で目立っていたその古年兵の信じられない去り際を、誰もが目に焼き付けていた。
死とは、不思議なものだった。
間近に迫るとその人間の上辺の皮を剥ぎ、本性を露わにする。
だとしたら――自分はどうなるのだろう。
弟や家族に、報せることが出来るものだろうか。
サリマンはそんな疑問を持った。
幸い運だけはよく、狙撃に長けた同室の戦友ほどの腕も度胸もないのに、彼は絶望的戦力差があり味方の八割が死んだクゼの丘でも生き残った。
――私が死ぬときは、老衰がいいけど。
――そうもいかんのだろなぁ。
遺骸(ゆいがい)となった戦友のタグを回収しながら、サリマンは自分の理想の死について悩んでいた。死地から帰る直前だというのに、人間の脳とはそう上手く切り替えられるようには出来ていないらしかった。
そのとき大きな声で名を呼ばれ、慌てて顔を上げる。例の同室の戦友だ。後方にあるタコツボの死体を担当しろというので、大人しく従った。
突貫工事で仕上げたタコツボはそれでも腰辺りまでの深さがあった。しかし今は転げ落ちた死体のためそれを踏んで歩くと足首から上は全部丸見え。これじゃあ上に積み重なってる奴はろくに隠れられなかっただろう。一つの骸のかっぴらいた眼球をとことこ歩く羽虫が羽音を響かせて飛ぶのを手で払いつつ、黙々とタグを回収していった。
と――そのとき。
金属を地面に引き摺るような嗄れ声が聞こえ、サリマンははっと顔を上げた。人間の声だ。他にいた数人の兵士も気付いたようで周囲を見回すと、死体らの隙間から伸びた手の指先がひくひくと震えていた。
――生存者だ。
「待ってろ!」
一番近くにいたサリマンが、重力のままに寝そべる死体を退ける。正直もう身体中の筋肉が役割を放棄する寸前くらいに疲労が溜まっていたがそんなのにかまっている暇はなかった。腐臭にまみれて暗い中に埋まっている状態なんて、ひどい恐怖だったろう。二人目を退かした先にいたのは――果たして、緑の軍服を着た戦友ではなかった。
鉄の国を示す黒い軍服。
スモークォの兵士だった。
「――ッッ!」
一緒に掘り起こしていた仲間が、ほとんど反射に近い動きでその兵士の頭を蹴り上げた。ごろり、兵士の体が斜めに転がる。
「よさないか!」
サリマンは咄嗟に兵士を庇うように手を広げる。
「なに言って……ッ、こいつ敵だぞ!」
「そんなことわかってる! ここでの戦いは終わった! 戦道法に反する!」
「んなもんあってねぇようなもんだろが!!」
顔を真っ赤にして唾を飛ばし信じられないというようにきつく眉根を寄せる仲間がサリマンを睨む。凄まじい気迫に顔を伏せそうになりながらも、サリマンは背後に兵士を庇いながらその飢えた獣のような緑の双眸を見返した。
「どけキーガン」
「駄目だ」
「なら殺せよ」
仲間のささくれた手の平は、腰の拳銃に伸びていく。
「それも駄目だ」
「っなんでだよ……!」
「……」
サリマンは、ちらりと背にした兵士を見た。まだ輪郭の丸さが残っている。二十代前後といったところだろう。
「弟と同い年くらいなんだ」
意図せず下がった眉尻に、仲間は腰に向かって空を泳いでいた指先を止めた。しばらく納得いかないというように歯を噛み締めていたが、兵士が顔面を蹴ってもぴくりともしないのを見て危険はないと感じたのか「勝手にしやがれ」と吐き捨て、周囲で見守っていた他の仲間と作業を再開した。
「大丈夫か?」
振り返った先、敵兵は耳慣れない異国語でなにかを呟いていた。
「なんだ? 息が苦しいのか? それとも傷が痛むか?」
「ウォギ……ウォ、ギィ…………」
砲撃で被弾でもしたのかズタズタに皮膚が裂けている顔に配置された唇は辛うじてその形を保っている。そこから紡がれた言葉を、国際医師を目指していたサリマンは正しく理解した。
「『ウォギ』? 水か、わかった待ってろ」
残り一口分しか入っていない水筒を肩から外し、キャップを捻る。戦っている内に形が歪んでしまったのか、中々開かない。
四苦八苦して、もうちょっと待ってろと言おうとしたとき――
――サリマンは、気付いた。
それは五感が収集した情報によって無意識下に生み出された予想というより、実に人生の四分の一を戦ってきた兵士の勘に近かった。殺そうとしている。走った目玉は敵兵の手元に視線をなぞらせる。敵兵の指先は、その腰の小口径のリボルバーに届かんとしていた。
ここでサリマンが立ち上がり、背負った歩兵銃を構え、敵兵の心臓か頭部を撃ち抜くのには二秒もいらない。この重傷の少年より、一応狙撃兵として戦場を駆けたサリマンの方が遥かに早く出来るだろう。そうしようとして、しかし同時に彼はもう一つのことに気付いた。――今が、自分の死の間際になり得る瞬間なのだと。
戦場に来た殆どの人間が、家に帰る頃には別人になる。皿が割れる音でパニックを起こし、笑い合っている男女を皮肉るようになり、兵隊ごっこをする子供がキラキラした目で見てくるのに耐えられなくなり、感情がコントロール出来なくなって、敵に容赦がなくなる。やがてそうしている内に恐怖が魂の奥底に根を張って、自分の本性と呼ばれるものになっていく。
死ぬ直前、人はその本性を露わにする。
では自分は――?
ビリッと音を立てて、脳裏を記憶が過ぎった。肺炎をこじらせて咳をする弟の背中をさすってやったときの、「ありがとう」と言われた嬉しさと切なさを。
そして同時に、昨日までの戦場の光景も重なって浮かび上がる。突撃してきた敵兵に無我夢中で銃剣を突き出して、手から肘に向かって命の残滓が這ったときの、両の瞳を潰され暗闇に突き落とされたかのような絶望、そして、再び朝を迎えることの出来たかのような安堵――。
弟に見せた医師を目指した姿か。それとも兵隊さんごっこをする子供の憧れであった兵士か。
サリマンの思考に使った時間は一秒に満たなかった。彼は一つ瞬きをすると、水筒のキャップを力一杯捻った。
「……ほら、水だ」
愚かなことだと、わかっている。わからないほどサリマンは子供ではない。けれど――これが最期の瞬間として選択出来るのであれば、兵士としてではなく医師を目指した男として終わらせたかった。そして、この敵兵が喉を通った温い水に涙して、考え直してくれることに賭けたかった。
喉仏が力なく上下し、そして。
――サリマンは、左胸を撃たれた。
「――、」
だよなぁという納得と、ちくしょうという悔恨が同時に胸に迫り上がり、それは血を含んだ空気として口から排出された。元々突いていた片膝がかくりと折れ祈るように両膝を突く形になった。サリマンがくすんだ緑の軍服がみるみる黒っぽい赤色に染まっていくのを視界に収めていると、銃口をこちらに向けていた敵兵の体が強張った。見ると、その側頭部を、吸い込まれるようにしていくつも弾丸が貫通していく。続いて騒がしくこちらに近付く焦りを含んだ足音。サリマン、と呼ばれた。
犬のように喘ぐ呼吸音がうるさく、仲間の言葉が上手く理解出来ない。
「意識ははっきりしてるな? 大丈夫だ、見せてみろ」
心臓近くを通った弾は太い血管を傷付けたらしく、手の平の中で壊れた蛇口から出る水のように出血しているのがわかった。どうやら声に出ていたらしく、同期が「大丈夫だ。肋骨と筋肉が守ってくれてる」と声をかけながら鎮痛剤を射ってくれた。傷を見るためだろう、彼の青年らしくも傷だらけの手がそっとサリマンの手を退かした。途端、コップをひっくり返したように血液が溢れ――ああ、駄目なやつだ、と苦笑する。実際はほんの少し口角がひきつっただけだったが。
「……キャスケット」
同期に、相応しくない呼び方だとわかっていても声を絞って呼びかける。
「なんだ」
「からだが動かない」
「……ああ」
「き、きずから、目が離せ……ない、んだ。自分が段々死んでいくのなんか見たくない……私は、家族のことを思い出しながら死にたい…………」
俯いたサリマンの口から、粘っこい喀血が、蜘蛛の糸が垂らされるように地面に落ちていく。
同期はその願いにただ一言、「わかった」と応えた。
そうして彼はサリマンの体を横たえさせると、濁りつつあるその両目の上に自分の手を重ねた。視界が暗闇に覆われると、情報量が少なくなって、サリマンは自分の感情と記憶に意識が向くようになった。
たまに兵舎裏に遊びにくる猫。
朝日に照らされる真夏の射撃訓練所。
日が沈む瞬間が一番怖かった真冬の行軍訓練。
大嫌いな古年兵。
連なる山。
広がる麦畑。
小さな小さな、田舎の風景。
その間を駆け回る、棒切れを持った小さな子供たち。
少し頼りないけど沢山の愛で育ててくれた母と、彼女が作るシチューが煮える音。
博識で愛国心の強い父と、彼の薬品と煙草の臭いがする分厚くて硬い手の平。
母の腹の中にいた一度も顔を見たことがなかった末の子。
賢くて優しい、自慢の弟。もう会えない。二度と頭を撫でてはやれない。抱き締めてやれない。彼が今、どれほどの苦しみや厳しさの中で生きていても、もう、頑張ったね、そう一言声をかけてやることさえ。
とりとめのない――けれど叫び出したくなるような――情景が心を撫で、あるいは突き刺す。そして、丘で綴った『追伸』――。
そのとき――薄灰色の雲の切れ間から天使の梯子が下りて。
「――…………」
サリマンは唐突に解した。
死とは、うちに帰れなくなることなのだと。
そして帰れないと解るから、自分のこれまでを振り返り、魂がなにかを遺そうとする。
死の間際の本性とは、遺骸(ゆいがい)の嘶(いなな)きのことだった。
――ではなにを遺すべきか。
――なにを、遺したいのか?
最後に過ぎったのは、弟と別れる際夏の日に奢ってあげた大衆食堂の檸檬ジュースだった。果実由来の酸味が程好いさっぱりとした味が、血泥に濡れているはずの喉に甦った。
――あぁ……帰ったら、あの日の檸檬ジュースを、また飲ませてやりたかった。
指の間からこちらを覗き込む同期の顔が見えた。すると、キャスケット帽の鍔の下で、その蜂蜜色の双眸がサリマンの言葉に了解したというように瞬いた。
それに安堵し、サリマンはゆっくり目を閉じる。
悔いがないと言ったら嘘になる。ないわけがないのだ。
けれど、この血濡れの丘で、最後までなにか綺麗なものが在るのではないかと信じ続けた自分の間抜けな性分。サリマンは、そんなどうしようもない愚かな自分の信仰が、そこまで嫌いではなかった。
――たとえ、死に直結したものだったとしても。
――たとえ、肉体は家に帰れなくても。
――私の魂だけは。
もう自分の足ではどこにもいけない。でもきっと、誰かが家族のところに自分の魂を届けてくれる。
サリマンは、蜂蜜色の瞳をした友人に見詰められながらそう信じた。
5
アルマンが家で泣く母と小さな妹を抱き締めていた頃、アルマンと別れ、町の入り口にある小さな役所を訪ねたキャスケットは、受付嬢に「姉さん、公衆無線機を貸してもらえないか」と帽子の鍔を押し上げた。
妙齢の受付嬢はしばし目をぱちくりとさせたが、すぐに「ああはい、無線機ですね。そちらをお使いください」とカウンター脇にある大きな背負い鞄サイズの無線機を指した。キャスケットは疲れたような掠れた声で「どうも」と言った。
「……兵隊さん、軍都生まれ?」
「ん……いや、生まれは南部だ」
「そう……? 年上の人を兄さん姉さんって呼ぶのは軍都のお方だけだと思ってたけど」
「ああ、オレの上官がそれだった。移ってしまったんだな」
受付嬢と会話をしながらも、キャスケットは無線機にカチカチと番号を打ち込んでいく。そうして数秒、受話器を手に取り耳に当てた。
《はい、こちらペリドット陸軍第一師団遺品返還部》
朗々とした若い兵士の声に、キャスケットも聞き取りやすさを心がけ咳を払う。
「こちらキャスケット上等兵。任務の終了を報告致します」
《……報告開始了解、ナンバー及び帰宅者と授受者の名前を》
「ナンバー十、帰宅者サリマン・キーガン、授受者そのきょうだいアルマン・キーガン」
《了解、ご苦労。……キャスケット上等兵》
「はい?」
《傍でベーゼ軍曹が代わるよう言っているのだが……》
相手の言い辛そうな声色に、それまで淡々と報告を行っていたキャスケットの顔が微妙にしかめられた。
「あー……汽車の時間があるんで、私はもう行かなくてはいけないとお伝えください」
《勘弁してくれ、目の前に本人いるんだぞ。この人じゃあ虚偽罪で本当に営倉に送りそうだ。代わるからな》
「あ、ちょっと」
抗議虚しく、受話器の向こうでがさがさと音がする。キャスケットは一瞬無線をこっちから一方的に切ろうかなと考えたが、次の任務の報告のときを恐ろしく思い止めておいた。間もなく音は止み、上品な男性の声が若い軍人に「やぁ、無理を言ったな」と呑気に礼を言う声が伝わってきた。
《キャスケット、私だベーゼだ。任務はどうだった?》
ベーゼ――コンスタンティン・フリッツ・ベーゼ軍曹。先の防衛戦争でキャスケットの直属の上官だった男だ。因みに彼は遺品返還部ではないし、今は士官学校に通い直しているため日中は忙しかったはずだ。
――この時間ならいないと思ったんだが……。
溜め息を呑み込む。
「別に、十人目にもなればもう慣れましたよ」
《そうかそうか、それならばいい。檸檬ジュースは奢れたかね?》
「はあ」
《キーガンはお前の同期だったし、話すことが多かったろう。お前は口下手だからなぁ、困らせなかったか?》
「……思い出を語れば、オレの主観が混じります。オレはあったことをそのまま話しただけです」
舌に油でも塗ったように喋るベーゼに対し、キャスケットは相手が上官であるにも拘わらず変わらずぶっきらぼうな言い回しをした。しかし相手はそれを咎めることなく、またそうかそうか、と子供が学校であったことを話すのを聞く親のような態度だった。
と――
《それでキャスケット上等兵、お前今日は何人撃ち殺したんだ?》
不意に、ベーゼがそんな物騒なことを訊いてきた。キャスケットは一瞬言葉を詰めたが、辛うじて取り乱すことなく息を吐く。
「……殺してませんよ」
ちらり、視線を転じさせる。剣呑さの滲む話題に受付嬢が怪訝そうにこちらを見るのを、下手くそな笑いで誤魔化した。
「軍曹、もう戦争は終わってるんですから」
《ん……そうか、そうだったな。つい癖で》
「直してくださいよそんな癖」
《善処しよう》
話題が途切れた。キャスケットは、サリマンの手紙を思い出した。血と油と煤に塗れた用紙。その姿が自分の胸元に入っている一通の手紙と重なった。端に焦げ跡がついた、かつて自分が受け取った手紙――。
一つ息を吸うと、キャスケットは「あの」と続ける。
「軍曹は……、あの日の、焼却炉の、こと……」
聞き取れなかったようで、相手が訊き返すように喉を鳴らした。キャスケットは迷うように口籠ると、「いえ、なんでもありません」と視線を伏せた。それから失礼します、と受話器を置こうとしたが、ベーゼが《ああそれと》と続けた。
《アルマン――だったか。そんな名前のキーガン家の次男がいるはずなんだが》
「……それがどうしたんです?」
《徴兵がかかった際その子も呼ばれたはずなんだが、母親が頑なにうちにもう男はいないと言ったそうだ。だが戸籍では確かに男となっている。キャスケット、なにかわからなかったか》
ベーゼは聡明な兵士だが、こういったことに態々首を突っ込むほど軍に対して忠義が厚いわけではない。おそらく、個人の興味が引かれただけだろう。そもそも彼だって、サリマンが戦場で弟が弟がと話すのを聞いていたはずだ。
それも悪い癖だ――キャスケットはしばし考え目を伏せた。
「さあ、わかりません。オレと同い年くらいのきょうだいはいましたが、中性的な奴で、男にも女にも見えましたよ。……どっちでもいいんじゃないですか」
投げやりにも聞こえる風に言えば、ベーゼはまたそうかそうか、と受話器の向こうで頷いた。
通信を終え、キャスケットは受付嬢に礼としていくらか金銭を渡し役所を出た。「別にいいですよ、兵隊さん」という彼女に「長電話だったから」と軽く手の平を翻した。
軍服の上からでも機能的に鍛えられたとわかる筋肉質な体躯、病人のように青白い顔色と生気を感じ取るのが難しい乏しい表情。枕元や暗い夜道に立たれたら、それを見た百人中百人が間違いなく「あ、出ちゃった」とか「げ、見えちゃった」と思うだろう。しかし二つ並んだ蜂蜜色の瞳だけが妙に多弁で、それだけが生者である証明のようになっているのが印象的だった。
そんな兵士だから、受付嬢は彼が去った後でもしばらく彼のことを考えていた。田舎の役所の受付なんていう暇な仕事だったからかもしれない。話した内容をなんとなしに復唱し、ふと、ある一つの事実に気付いた。
「……南部、って」
森に覆われた父国ペリドット、その端の端。多数の狩猟民族から成り立ったこの国の中でも、とりわけ高い身体能力を持つ一族が腰を下ろしていた地域。そこは数年前、隣国であり敵国スモークォに開戦の狼煙(のろし)代わりに戦略核を落とされ更地にされ、また放射能の影響によって外部から誰も入ることが出来なくなった場所だった。
帰る故郷がないから、あの仕事をしているのだろうか。敵国の攻撃機同様に『死神』と呼ばれ、忌み嫌われる仕事を――。
兵役を終えたであろう年齢の錆びた背中を思い出しながら、受付嬢はそんなことを口の中でだけ転がした。
軍事国家として成り立つこの国――ペリドット帝国の陸軍には、戦後に設置されたという変わった後方支援部が存在した。
名を『遺品返還部』。字の通り、死亡した兵士の遺品や遺言をその宛先へ送り届けることを役目とする部である。
しかしその部に所属する兵士が訪れるということはつまり、出兵した家族や友人が死んだことを意味する。故に青い鞄を背負った遺品返還部の兵は『死神』と呼ばれ、複雑な感情を向けられた。
伸び放題の雑草。きっと戦時中自分たちの兵糧の素にもなっただろう麦畑が脇にずぅっと続く田舎道を、役所を後にしたキャスケットはゆっくり歩いていた。
手元にある、やたら絵や図の多い青い手帳には、次に向かう授受者の所在地が書かれている。
「北部都市『金猫(きんぴょう)』……花街か」
『金猫』といえば首都や軍都を中心に点在する花街の中でも特に栄えている特殊商業都市だ。キャスケットもそっちに任務があった際、上官に連れられて何度か行ったことがある。迷うことはなさそうだ。
一枚のタグと、一枚の手紙と、一欠片の骨の分だけ軽くなった鞄を肩に負い直す。
死んだ人間の関係者に、死神のように「死にました」と伝えるこの任務ももう十回目で、授受者との関わり方も心得てきた。
「……」
けれど未だ、こうして一つの任務を終える度に頭蓋の中を満たす思いがある。
それがどれだけ無意味でどれだけ無意義なことでも、キャスケットが一人の人間で、そして自分も同じような状況で死んだかもしれないという可能性があった限り、その考えを止めることは出来なかった。
今こうして『帰った』彼らは死の間際、なにを感じたのだろうなどという、
――やはり無意味で無意義な、ありふれた疑問。