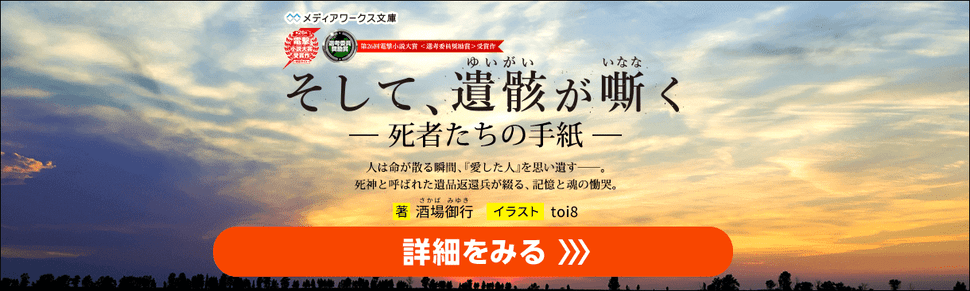2
二年後、統合暦六四四年。某工場地帯。
台に、一枚の金属板が置かれている。
ハンドルを下げると、上から逆さにした凸状の金型が下りてきて、板は下部で正反対の形をしている台に押し当てられた。再びハンドルを上げると、板は鍋の形を成していた。
作られた製品を型から外したら隣で作業する男性に手渡す。再びプレス機に金属板を設置し、ハンドルを下げ、上げて、開いた金型から外して――この上下運動を、朝の七時から昼の一時まで延々と繰り返す。許される休息は九時のトイレ休憩のみ。けれど、この工場では一日中この立ち仕事をしている者もいるのだから、マシな方だった。
「アルマ!」
流れるような作業で金属板を手に取ったとき、騒がしい工場内で相手に届くようにと張られた声が背中に届いた。板を慎重に置いて振り返ると、工場長が紙を挟んだバインダー片手に機器と労働者たちの間を縫うようにして足早に歩み寄ってきた。「はい」と返事をすると、大きすぎるほどの声で「お前、来週の日曜は空いているか」と問われる。
「はい」
「本当か!」工場長は、ほっとしたように顰めていた眉をほどく。「ニックが葬儀で来れなくなっちまったんだ。夜勤の時間帯になるんだが、出れないか」
「わかりました。十七時から八時ですね?」
「ああ。頼む」
そのとき、昼時を知らせるベルが鳴り響いた。アルマ――そう呼ばれた少女は、ベル音が聞こえる方を一瞥してから、「今日はこれで上がらせてもらいます」と頭を下げ、更衣室の方へゆっくりとした足取りで歩いていった。
「アルマっていうんですか、あの子」
シフト表を書き直していた工場長に、横で作業をしていた男性がアルマの背中を見送りながら声をかけた。
「ん……ああ、二つ隣の町の子だよ」工場長が答える。
「二つ? 川の向こうの? またえらく遠いとこから来てますね。別に給料が高(たけ)ぇまけでもねえのに……。訳アリですか?」
「さあなあ。父親が軍医とは言ってたが」
「だったら尚更そんなに金いらねえじゃないっすか。女の子がやる仕事じゃないですし」
「色々あるんだろ。どこの家も親父や兄貴は兵隊に行っちまって大変だろうしよ。お前は運良く帰ってこれたみたいだが」
「はは。まあ、なんとか」
男性はへらりと笑った。その片耳は楕円形に欠けていて、工場長はそれを一瞬だけ視界に入れると「お前も休憩入れよ」と言い残し、去った。
アルマは着替えを終えると工場の裏口から外に出た。夏の暑苦しい太陽が彼女の肩に重く圧し掛かり、背中を丸めて俯くようにしながら砂利道を進む。鉄色の工場を囲むフェンスを越えた先には草木が生い茂り、彼女は獣専用としか思えないような一本道をゆっくりと歩いていく。
彼女の住む町は、この工場から徒歩で一時間と三十分の場所にある。元々国自体が自然豊かだが、彼女の町はその中でも特に田舎だと言えた。森と山ばかりで、産業地区から離れると濃い緑葉の臭いが鼻の奥をぐりぐりと掻き回した。
休むことなく歩き続け、斜面に沿うように進んでいた山を抜けた。獣に出くわすことがなかったことに安堵しつつ少し歩くと、今度は道の両脇に整頓して並べられたような麦畑が広がるようになった。もう町に到着した証拠だ。
――爪先が痛い。
そう思って、足を止めた。ブーツのサイズが合わなくなったのだろうか。それとも爪が伸びてきていたのか、ただ単に歩き過ぎか――いずれにしても痛みは変わらない。だから停止した。それだけだった。しかし、
「――おい!!」
畑から怒気を滲ませた声が飛んできた。太陽色の麦穂の中から、年老いた男が鎌でこちらを指していた。吊り上がったぼさぼさ眉の下の目は血走り、アルマが何も答えないでいると麦を掻き分け大股でこちらに寄ってきた。
――ああ、またか。
アルマはその場から一歩も動かずに老人の到着を待った。老人は鎌を握り締めたまま、両腕を前へ後ろへ乱暴な振り子のように振りながらアルマに近付いて、顔を突き合わせた。
「てめえ! オレの畑でなにをしてやがった!!」
「……、」
「立ち止まってなにをしていた!!?」
ニキビだらけの顎の上、歪んだ口から唾を撒き散らしながらしゃがれ声でありもしない罪を問う老人。アルマは彼の土がついた顔の向こうにある麦畑を見ながら、しょんべんみたいな色だな、とぼんやり考えた。
「聞いているのか! 貴様のような卑怯者が何をするのかオレにはわかるぞ、わかっているんだ! いいか、二度とこの道を通るんじゃない! オレは『さもなくば』なんて脅しをする気はない――次にお前を見かけたら鎌で喉を切り裂くからな!!」
老人は鎌を持ったままの手でアルマの胸を突き飛ばした。小柄な体躯は抵抗する間もなく弾かれ、道の縁に仰向けに倒れた。老人は憎々し気に唾を吐きかけると、アルマの足元で砂を蹴り上げ「立ち去れ!」と怒鳴った。
アルマは一切口を開かず、這いずって立ち上がるとよろけながら走り出した。その様子を、周囲の畑で麦の手入れをしていた町の人間が見ていたが、誰一人として仲裁することはなかった。
誰もかれもがアルマに軽蔑の眼差しを向け、老人の行いが正しいことのように黙認した。
ペリドット国の西の端に位置するこの小さな町は、田舎ながらも物流の途中にあることもあり戦時中でも配給なしでそこそこ食料が手に入った豊かな場所だ。アルマの家はその東にひっそりと佇んでいる一軒家で、父が存命だった頃に建てたものだった。
「ただいま」
泥と砂で色の変わったスカートを玄関前で軽く払ってから中に入ると、リビングの方から「おかえりー!」と子供の声が返ってきた。続いて、ととと、と軽い足音がして、妹が顔を出した。
「おねえちゃんお帰り……わあ! お洋服どうしたのー?」
「帰り道で転んだ。母さんは?」
「お庭! 洗濯物!」
砂まみれだというのに腰に抱き付いてくる妹。「汚れるよ」と言っても聞かなかった。嬉しそうに頬を押し当ててくる彼女に、微笑ましい気持ちになる。離れようとしない妹を抱き上げて、リビングを通って庭に面したベランダに出た。
「母さん。ただいま」
洗濯物を取り込んでいた母に声をかけると、肉の薄い頬がこちらを向いた。細い腕、細い足、血色の悪い皮膚にほつれた髪。母はアルマの姿を認めると、悲痛そうに眉根を寄せた。
「どうしたの、アルマ……。また怪我を?」
「ううん。山で転んだだけ。一昨日雨が降ったでしょ、それで道がぬかるんでて」
予め用意していた言葉を淀みなく吐き出すと、素直な性格をしている母は納得したようだった。「まあ」と声を漏らし、手に持っていた籠を置くとアルマに近寄った。アルマも妹を下ろしてそれに応える。母は手の平の擦り傷以外に目立った外傷がないことを確認すると安心したように肩を下げ、シワの目立つ手をアルマの頬に当てた。
「ねえアルマ、やっぱり無理してあんなに遠いところで働かなくてもいいのよ。父さんの貯金が残っているし……お金よりも貴方のことが心配だわ」
「……でも、ウチは男手がないでしょう? 何があるかわからないし、今のうちに稼いでおきたいの」
「でも……」
「心配しないで。工場の人は良(い)い人が多いし、余計なことも聞いてこないから、結構楽しいの」
笑いかけると、母はアルマの頬から手を離した。互いに誤魔化すような微笑みを浮かべ、先に目を逸らしたのは母の方だった。母は妹に替えの服を出してやるように言って、洗濯物の取り込みを再開した。
先にタンスの方へ走っていった妹に続いてアルマもリビングに戻る。一軒家と言っても大きなものではないため、台所も風呂場もリビングからは一目で様子が分かった。シンクに食器が溜まっている。一週間前に少しでも気分が上向くようにと買った花は鉢の上で萎れ始めていた。そして、家中どことなくかび臭い。吐きそうになった溜め息を呑み込むと、妹がベランダとは反対方向の、家の前が見える窓に張り付いていることに気付いた。
「……? どうしたの?」
「おねえちゃん、へーたいさん」
「え?」
アルマは目をぱちくりさせて外を見る。そこに、家の玄関に近寄ってくる人影があった。
光の加減によっては黒くも見える濃緑色の軍服を着用した男性。折り襟に凝ったデザインという将校服ではなく、一般の兵士が着る詰め襟にやや質素なデザインのそれだ。
「――!」
――兵士。
――まさか。
どくりと、蠢くように心臓が血を歪に送り出す。呼吸が浅くなり、自分の身体の末端から血の気が引いていくのがわかった。逆光で兵士の顔はよく見えない。どうすべきかわからずに、ただ軍服姿が玄関に近付いてくるのを妹の後ろで見送っていると、間もなく鳴ったコンコンというノック音で我に返った。
――どうしよう。
――だって、この家に来る『兵士』なんて。
一人のときだったら居留守を使ったかもしれない。けれどこの場には母も妹もいる。案の定、ノックの音が聞こえたらしい母が「アルマ、お願い」と声をかけた。
出ないわけにはいかない。アルマは上手く力の入らない足のまま、玄関に向かう。そのとき、
――あ、服……、
最中に自分の恰好を思い出して、彼女は自分の首から下を見下ろした。泥と砂のついたブラウスとスカート、女物のブーツ。着替えなければと思ったが、急かすように再びノックされて、う、と声を詰まらせながらドアノブに手をかけた。
「……」
けれど。中々そこから指を動かすことが出来なかった。扉一枚隔てた先で、それさえなければ吐息すら肌に感じるであろう距離に、彼がいるかもしれない――途端、彼女の腕が微かに震え、握ったドアノブがかちかちと音を鳴らした。生じたのは、間違いなく恐怖だった。アルマはいくつか息を吐き出し、長い時間をかけて、ようやくドアノブを捻ることが出来た。
扉の先に立っているのは。彼だろう、と――もう会わないであろう人だと思った。終戦から二年。報せは来ないが、きっと戦死したのだろうと。けれどこの家を訪れる『兵士』なんて、彼しか考えられなくて――。
「――兄、さ……」
その呼び名を、随分久しぶりに口にした。
だが。
「――……」
――違う。
そこに立っていたのは、古い記憶の中で笑っていた彼女の兄ではなく、マリン・キャスケットを被った見知らぬ兵士だった。
「え……」
「……キーガンさんですか?」
兵士は扉にかかった表札にちらりと視線を流しながら、彼女にそう訊いた。想像と違う人間の存在に混乱した彼女はやや反応に遅れながらも、ゆっくり頷く。
すると兵士は、手にしていた小袋から、一つの認識タグ、白いなにかの欠片、それから封筒を取り出す。――それらの全てに乾いた血が付着しているのを見て、彼女は兵士が何者で、そして自分の兄がどうなったかを理解した。
「ペリドット陸軍遺品返還部です。第一師団第三連隊第二大隊特殊遊撃中隊所属サリマン・キーガン一等兵は、クゼの丘で名誉の死を遂げました」
兵士は手の平に乗せた三つのものを見詰めるように頭(こうべ)を垂れ、「ご苦労様でした」と続けた。
そのとき彼女は、頭の中が重い水で満たされたようになにも考えられなくなり、差し出された三つのもの――遺品を受け取れなかった。そうして数秒時が流れると、彼女の背後で、ドサリとなにかが落ちる音がした。はっとしてそちらを向くと、玄関の奥に外から取り込んだ衣類を床に落とした母の姿があった。
「母さん……」
「『死神』」
母が、虚(うろ)が空いたような瞳でそう呟く。
兵士が母に向かってなにか言おうと首を伸ばしたとき、母は間髪容れず「出ていって」と続けた。
「出てって……出ていって!! 息子は生きてます!」
「あの、」言い募ろうとする兵士に母は足早に近寄り、己よりも背が高く分厚い肩に掴みかかった。
「なにが名誉の死ですか! お願いだから出ていって頂戴!!」
兵士は顔を伏せ、数歩後ろへ下がる。彼女の小柄な母の力のみでそのように押し出せるはずはない。兵士は、母の意思に沿おうとして自ら下がったのだろう。久方ぶりに叫んだ母は、ぜえと息を吐き出しながら震える指で玄関に鍵をかけると、そこに背中を凭れて座り込んだ。
「母さん……」
「う、ぅう、ううぅ~、うぁあ~~」
母はシワと荒れの目立つ両の手で顔を覆い、幼い少女のように泣き出してしまう。騒ぎを聞き付けた妹は部屋の入り口から不安そうな顔を覗かせて「喧嘩?」と訊いた。それに、「なんでもないよ」と返す。
母はしばらく泣き止まないだろう。無理もない、父が死んだという通達があってから、まだ一週間だ。立て続けに家族が二人も死んだ報せを受けて泣かぬ者がいるのならその強靭な心を母に伝授してやってほしい――そこまで考えて、彼女は、それが自分自身のことであることに気付いた。
――涙の一つも出ないものなのか。
何故だろうと、考えるまでもなかった。
自分は安堵しているのだ。兄が帰ってこなかったことを喜んでいる。しおらしく母の背中を撫でていながら、自分の心の底にいる本性は「兄さんが死んだ! よかったよかった!」と万歳をしているのだろう――アルマはそう考えると、かび臭い家の中で、ああ、洗い物を済ませなきゃな、と目を伏せた。
母の情緒が落ち着くのには半日かかった。
アルマは翌日の朝、母には市場に食料を買いに出ると言って家を出て、昨日の兵士を捜しに行った。
アルマは町の中心部にある市場の賑わいを抜け、まだ滞在しているのなら朝食を食べているだろうと見当をつけると町で一番目立つ大衆食堂へ歩を進める。
その道中、彼女に声をかける者は誰一人としていなかった。小さな子供はその傍を歩く大人に強引に手を引かれてアルマから遠ざけられ、大人たちは草が揺れるような小さな声で彼女について何事か口にした。聞き取れた単語は、「みっともない」と「卑怯者」だった。一切を無視して足早に進む彼女の背に、突如衝撃が襲った。
「ッ」
たたらを踏んでなんとか転ばずに済む。振り返ると、四、五人の子供が剣と旗を模した棒きれを手にして笑っていた。
――ああ。
――『兵隊さんごっこ』か。
「『ヒコクミン』討ち取ったりー!」
内一人がそう言って、きゃははと前歯の無い口で無邪気に笑い声を上げた。ヒコクミン、非国民――恐らく親の真似だろう。子供たちはそのまま踵を返すと、蜘蛛の子を散らすように駆けていった。それを咎める大人はおらず、むしろどこかから嘲笑が耳に届いた。アルマも同様に、子供らを怒ったり注意するような真似はしなかった。紛うことなき、正論だったからだ。
誰とも一言も言葉を交わさぬまま、彼女は痛む背中を手の甲で拭うように擦ると、また静かに歩き出した。
食堂に着くと、他の客が驚いたようにアルマを見て、次いで侮蔑にその眉を顰めた。顔見知りの女将はそれまで振りまいていた笑顔を一転させ、煩わしそうにアルマを出迎えた。
「……何の用だい?」
歓迎の対極にあるような声色。彼女の傍で配膳を手伝っている隻腕の青年も似たような態度で、アルマを一瞥して直ぐに目を逸らした。
「……お店に、兵隊さんが来ませんでしたか」
「ああ、来てるよ。奥の席」
女将が顎で指した先に背伸びをして視線を伸ばすと、何人もいる客の後ろ姿の向こうの向こうに濃緑色の軍服が見えた。頭には昨日と変わらずキャスケット帽を被っていて、その陰にテーブルに立てかけられた歩兵銃の頭が見えた。
女将に「ありがとうございます」と言い、店の奥へ進む。
「兵隊さん」
呼べば、青白い顔が振り返った。
キャスケット帽の下の顔付きは、兵士らしい厳かさの中にどことなく品の良い雰囲気を感じさせる精悍なものだった。しかし恐らくアルマとそう歳の変わらない――あるいは少し上くらいの――二十代だろうに、目の下の隈と荒れた肌のせいで老けて見える。病人かそれとも亡霊のような印象が濃いが、ただ気怠そうな蜂蜜色の瞳だけが、生々しい有機的な視線を彼女に向けている。
「……昨日の」
「はい、サリマン・キーガンの妹です。昨日は母がごめんなさい」
「いや、いいんだ」
兵士が視線でアルマに椅子に座るよう勧めたため、アルマは素直に従う。次いで、彼は女将に柑橘系の飲み物を注文した。
「……あの……兄が戦死したというのは」
指先で熱したものにおそるおそる触れるように問うと、静かな首肯が返ってきた。「そうですか」、苦笑いを向けると、兵士はやや怪訝そうに首を傾げた。
「……お前は、大丈夫なのか」
「……?」
「兄が死んだのに」
曇り硝子の向こうからこちらを覗き込まれたような気分だった。そうだ、当然だ、兄が死んだのに冷静な方がおかしいのだ――アルマは唾を嚥下するとなんとか口を開いた。
「え……、ええ、まあ。あまり兄のことは覚えていないですし、私まで泣いてしまったらお話が進まないでしょう?」
「………そうか」
不躾だとは感じたが、彼は気遣って言っていたのだろう。アルマはこの兵士が悪い人間ではないことを理解した。少なくとも、自分よりは善い人間だ、と。
そのとき、先程注文した檸檬と砂糖を煮詰めて作ったジュースが届いた。随分可愛いものを飲む兵士だと思いきや、どうやらアルマ用だったらしい。兵士は黙ってグラスをアルマの方へ寄せた。どうしてこれを頼んだのかはわからないが、一先ずありがとうございます、と受け取り、少しだけ口をつける。なんとなく、懐かしい味がしたような気がした。
「兄は……なにを残しましたか?」
騒がしい店内でそう問えば、兵士は青い肩掛け鞄から昨日の小さな袋を取り出し、中身を卓上に置いた。
タグと、手の平のサイズの白い物体。前者はサリマン・キーガンの戦死報告用のタグだが、アルマには後者がなんなのかわからなかった。
「これは?」指を差して問うと、兵士は「キーガン一等兵の肋骨の欠片だ」と端的に答えた。
「……本当に死んでしまったんですね」
「そうだ」
アルマは、遺族を気遣うくせにいやにはっきりとした兵士の受け答えに苦笑した。遺品を受け取り礼を言おうと思ったが、そこでふと、昨日はもう一つ、大半が赤黒い色をしていた白い封筒も持ってきていなかったかと思い出す。
「兵隊さん、昨日のお手紙みたいなものは……」
「あれは弟に渡せと頼まれたものだ」
「……弟、ですか」
「今家にいるのなら届けるが」
グラスの中で、溶けて形を変えた氷が小さく転がりからりと音を立てる。がやがやとうるさい店の中、二人の間でのみいくらか沈黙が落ちた。
「……弟も戦死したか」黙ってしまったアルマの心情を想像し、兵士がそう訊いた。
「いいえ、生きています。生きていますが、在りはしません」
「……? どういう意味だ?」
「弟は……」
それ以上言葉が出なかった。アルマはそれを誤魔化すようにジュースを口に含む。こんな暑い日にぴったりな、爽やかでひんやりとした味が喉を通るけれど、彼女はその美味しさの半分だって味わえなかった。
兵士は彼女の様子を見て問い詰めるのは野暮だと考えたのか、「出直すか」と問う。
「いえ………その手紙、私が弟に渡すわけにはいきませんか」
「それは出来ない。必ず本人に直接、と言付かっている」
兵士の答えに噛み締めた唇から、檸檬の風味がした。
結局その日、アルマは兄の遺品を受け取れなかった。
俯いた気分で家に帰ると、母はまだベッドの上だった。
「遅かったわね」
ぼんやりと掠れた声。
「休日だから市場が混んでたの。体調はどう?」
「……あんまりよくないわ」
「まだ寝てなよ。夕飯、私が作っとくから」
「そう? ありがとう、アルマ」
弱々しく眉尻を下げ、母は「こっちいらっしゃい」と手招きした。それに従いアルマがベッドの脇にしゃがむと、母はアルマの後頭部に手の平を回し自分の額に引き寄せ、長く伸ばした髪を撫ぜた。
「アルマ……どうかお前だけはどこにもいかないでね……お願い……、私をうちに置いてかないで……、もううちに死神を寄越さないで……」
母の冷たい指の間を、アルマのありふれた焦げ茶の髪が通っていく。アルマは、儀式のように定期的に唱えられるその言葉に、やはり儀式的に頷いた。そんな最中脳裏に過ぎったのは、町の子供が笑いながら自分の背中を棒で叩いた姿だった。
昔、近所の同い年くらいの子供たちと一緒によく遊んだ。花占いから川遊び、鬼ごっこ、腕相撲にボール遊び。色々なことをしたが、一等人気だったのは、あの子供たちと同じ――長い棒きれの先に旗を括りつけてそれを振りながら駆け回り架空の敵兵と遊ぶ『兵隊さんごっこ』だった。
アルマ含め、友達も兄弟のいる子が多かったから、兵隊さんごっこでは兄弟間で『小隊』を作ることが多かった。兄と弟。姉と弟。兄と妹。姉と妹。皆嬉しそうに兄や姉の腰に抱き付いていた。
――「お前も兄ちゃん呼んでこいよ」
友達に無邪気に笑って言われて、アルマは小さく頷いた。
――「お兄ちゃんお兄ちゃん、遊んでよ。兵隊さんごっこすんの。お兄ちゃん、今日はお勉強ないでしょ。だって学校お休みだもん。今日こそ遊んでよ。小隊長役やってよ」
幼いアルマは毎日そうやって強請ったが、兄は毎度首を縦に振らなかった。医者になるための勉強で忙しいから、また今度ね。また明日ね。また来週ね。困ったようなその顔ばかり、覚えている。
トボトボと友達の下に帰ると、必ず言われた。「ほら、お前ん家の兄ちゃんは弱虫だ」「戦争に行っても一番に逃げ出しちゃう『脱走兵』だ」。笑われても、反論が出来なくて、悔しかった。
自分は兵隊さんごっこでいつも大将首を取るほどに活躍するのに、その兄は弱虫呼ばわりをされる。みっともなくて嫌になる。兄のせいで自分までみっともないと思われる。
当時はそれにいじけて地団太を踏んだけれど――同時に、毎日遅くまで勉強しているその姿に、よっぽど医者になりたいのだろうと幼心に理解した。そして、兄は兵士にならない代わりに、病に苦しむ世界中の人を助ける存在にいずれなるのだろう。そんな風に考えては自分を慰めた。
けれど、兵士になったのはアルマではなく兄だった。
皮肉なことだ。
『兵隊さんごっこで活躍して家に残った自分』と『兵隊さんごっこを拒絶し続けたが戦争にいった兄』。どちらが立派か。どちらが弱虫か。長い間考えてきたが、答えは直ぐに出た。
兄と父を戦争に取られてから、腹の中に妹がいるというのに父と兄を軍に奪われた母は少しおかしくなって。
ある日の朝目が覚めると、アルマの部屋のドアの前には長い丈のスカートとフリルのついたブラウスが置かれるようになったのだ。